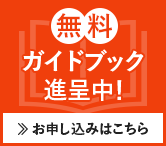少し前の話題となりますが、2011年7月27日の「人材育成・研修ニュース」に是非注目して欲しい記事を見つけました。
ポジティブドリームパーソンズ
経営人材の新評価制度「リスペクトサーベイ」を開始-上司、同僚、部下の360度方向から評価
主なポイントは、
- 経営チームの強化策として実施
- 経営チームにとって必須なことは「人望」
- 「人望」という抽象的なものを「リスペクト」の度合いとして定量化する
- 「リスペクト」の評価ポイントとして、儒教の教えである「五常の徳」を引用
- 「仁」「義」「礼」「智」「信」をベースとした10個の評価項目を設定
- 業績評価に次ぐ指標として位置づけられ、年に1回評価実施
- 経営チームへの意識改革
- 部下は経営チームに何が望まれることなのかを考える機会になる
とても良い使い方をされているな…と正直思いました。
ポジティブドリームさんのこの仕組みについては、「仁」「義」「礼」「智」「信」をベースとした評価項目など、面白いな〜と感じることが多いです。
その中で、今回取り上げたいのは、「人望」ということです。
個人的なことですが、この「人望」については、懐かしい想い出が蘇えってきます。
今から10年以上前。
私は大手メーカー(当時、誰もが認める優良有名企業)において次世代リーダーの選抜・育成の仕組み設計のコンサルティングを行っていました。
当時の日本においては、「次世代リーダー育成」、「サクセッションプラン」に取り組んでいる会社はまだ少なく、先行事例はGE、IBMなど海外企業が中心。
日本では、コマツさん、ソニーさんなどほんの一部の企業が、模索されながら取り組まれているような状況でした。
そのコンサルにおいて、議論となったのは、普通の管理職選抜ではなく、役員選抜という場面において重視すべき要件をどう考えるのかということでした。
いろんな議論を経て、最終的に「人望」という要件に落ち着いたのです。
選抜(昇進含む)は、対象者自身の問題だけではありません。
その対象者が属している組織や関係者にも良くも悪くも大きな影響を及ぼします。
その最たるものは、周囲(部下・関係者)の納得感がない選抜です。
これはメンバーの士気を低下させ、組織力を間違いなく低下させます。
例えば、
「え〜っ、なんであの人が選ばれるの?人事部は現場のことをわかってないな…。」
「あの人、上にはいい顔をしてるけど、部下からは信用ないし、組織のことを本気で考えていない。あんな人の下では働きたくない…。」
こんな話が現場でささやかれ、その不満話は組織全体に蔓延していきます。
同時に、本来評価すべき優秀な方のモチベーションを低下させてしまうでしょう。
このような抜擢・昇進人事によって、組織の状態が悪くなってしまった会社を何社も見てきました。
人事部からは意外と見えにくいことなのですが、このことは、人事部や経営に対する不信感を生み出します。
課長クラスの昇進ならまだしも、部長クラス、役員ともなると、その選抜された人が将来的にはその会社を担っていくことになります。
つまり、その人の指示によって、会社が動いていくことになるわけです。
そう考えると、将来の会社に対する不安感、そして不信感が増すのは当然のことでしょう。
「あの人の下で働きたい!」「あの人のためにも頑張りたい!」
部下をそういう気持ちにさせるのは、まさに「人望」。
だからこそ、役員や上級管理職に求める要件として、「人望」はとても重要な意味を持つのだと思っています。
しかし、難しいのは、この「人望」をどうやって評価するのか?ということです。
通常の上司評価だけで、本当に「人望」というものを評価できるのでしょうか…。
そもそも「人望」とは何なのでしょうか?
“信頼できる人物として、人々から慕い仰がれること”
と、辞書(大辞泉)には記されています。
当たり前ですが、大事なポイントは、「人々から」ということです。
「人望」は、複数の人々の感情によってつくられた状態のことです。
そんな状態を1人の上司が正しく把握できるわけがありません。
それだけに、今回のポジティブドリームパーソンズさんの「人望」を評価する仕組みとして、複数人の関係者(特に部下)が関わる360度フィードバック(360度評価)を活用されているのは、とても理にかなっています。
感情をあなどってはいけません。
理屈抜きで、人や組織を動かす原動力となるものです。
組織の活性化や強化を実現するためには、「人望」といった目に見えない集団の感情も含め、現在の組織を把握することが欠かせません。
現状を正しく把握できていない、つまり問題状況が曖昧なままに、その解決に向けて適切な施策を行うことには無理があります。
「人望」などの感情を含めた組織や個々人の状態をいかに把握するのか。
360度評価には、まだまだメジャーとは言えない“深くて有効な”活用方法がありそうです。