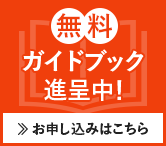弊社は創業以来約300社の360度フィードバックの導入に関わってきました。
想定以上の効果があり、なくてはならない経営・人事施策として定着している企業も多いです。
弊社でご支援した成功事例をじっくりと眺めてみると、「成功」する企業に共通する「3つの特徴」があることが見えてきました。以下が成功する企業の特徴です。
1. 「導入の目的を明確かつ具体的に設定」し、その「目的に合わせた設問や報告書の設計」をしている
2.「個人結果の返却方法」を工夫している
3.「結果返却後のフォロー」を工夫している
1つずつ、ご紹介していきます。
<① 「導入の目的を明確かつ具体的に設定」し、その「目的に合わせた設問や報告書の設計」をしている>
アタリマエのように思えますが、意外なほどこの目的があいまい、または具体的でない企業が多いです。
検討の「背景」や「解決したい人事課題」を踏まえて、“自社での導入目的”を“具体的”に設定することが大変重要です。
では、なぜ目的を明確・具体的に設定する必要があるのか…。
360度フィードバックは、やり方を工夫(カスタマイズ)することで、その効果を大きくできるツールなのですが、カスタマイズのベース(軸足)となるのが、この「導入目的」です。
導入目的を具体的にしておくと、「設問設計」「回答者選定」「報告書フォーマット」「結果返却方法」などに、いろいろと工夫でき、効果も高まります。
最近のご支援事例で多いのは、「設問」のカスタマイズです。
テーマは以下のようなものが多いです。
- 「管理職の部下育成力を強化したい」
- 「管理職の自覚なきパワハラをなくし、部下が本音を言えるようにしたい」
- 「挑戦する組織を創りたい」
- 「風通しの良い組織を創りたい」
など
このように目的を踏まえた設問にすることで、自社の管理職に求めたいこと、変えていってほしいことなどが「経営からのメッセージ」として、対象者のみならず回答者にも明確に伝わっていくことも利点です。
<② 「個人結果の返却方法」を工夫している>
これも成功のために大変重要なポイントです。
経験上、「社内便で送付」や「イントラネットでダウンロード」のように単純に結果を返却するだけでは、効果がなかなか高まりません。
その理由は、この方法だと「じっくり結果に向き合わない」人もいるからです。
- そもそも360度フィードバックの目的を誤って理解しており、実施自体に反発しているから
- 結果の正しい見方を知らないから
例:「結果を少し見ただけで、わかった気になる」「自分の意に反した結果で、目をそらしてしまう」といったことが考えられます。
では、どのように返却すると効果が出やすいのか。
オススメは、「フィードバック研修・説明会」をきちんと行うこと、そして内容を工夫することです。
フィードバック研修を行うと行わないでは、対象者の結果の受け止め方や施策に対する満足度などに大きな差が出ます。
内容は、
- 施策の意味を正しく理解する
- 結果に対してしっかりと向き合い、自己の結果を受けとめる(気づく)
- 気づいた強みをさらに生かす、課題を改善する計画を立てる
といったオーソドックスなものですが、設計する際の、「モチベーションを高める(下げない)工夫」や「気づきを現場実践につなげる工夫」などが重要になってきます。
このようなフィードバック研修を行った上で、現場に戻って上司と実施結果を見ながら面談し、現場でどう行動するかなどを話し合えれば、さらに効果は高まります。
<③ 「結果返却後のフォロー」を工夫している>
ドイツの心理学者エビングハウスの「忘却曲線」という説をご存知でしょうか?
覚えたり学んだりしたことを、「1日後には75%近くは忘れてしまっている」というものです。
この“人は忘れる生き物である”という前提に立った支援が重要になります。
- 行動計画立案1週間以内に、リマインドメールを送信する
- 実施3か月後に、上司との面談を設定する
など、結果から気づいたことや立案した計画を思い出させることが継続的な現場実践への支援となります。
とはいっても、結構パワーがかかる(本人・上司・人事)施策ですので、これらをやりとりできる“システム”を活用すると、運用負荷が軽減できることでしょう。
簡単に「成功のポイント」をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。
360度フィードバックは、その効果性も高いツールとして、多くの企業でご好評をいただいていますが、一方で、導入の仕方いかんでは“劇薬”ともなります。
しかし、上記のようないくつかのポイントを踏まえれば、大変有効な成長支援・組織力強化のツールとなります。
各ポイントの詳細をお伝えしたいのですが、紙面の都合上、多くは語りきれません…が、「360度フィードバック活用ガイド」にできるだけポイントを記載しております。
ぜひご覧いただければ幸いです。